我が家の長男もち氏は、ひどい猫風邪をひいて保護されました。そのせいか、風邪をひきやすくて、体調の変化が少しでもあると気になってしまいます。かれこれ4年ほど一緒に生活してますが、年に1回程度は体調を崩したりします。猫は病気を隠すのが得意な動物ですので、日頃から猫様の様子をよく観察し、病気のサインにいち早く気づくことが、早期発見と治療につながります。我が家はまだ風邪程度の病気ですが、年齢が上がってくるともっと大きな病気になるのではと心配ですよね。
ここでは、猫が特になりやすいとされる病気トップ5について、その症状や発症しやすい年齢、予防法を詳しく解説します。
あ、ちなみにくも氏は全く風邪すらひかない元気な暴れん坊将軍です。去勢した日も術後に普段通り大暴れしていました💦とはいえ、くもの様子もしっかりと観察してますよ!
1. 慢性腎臓病
猫が最もかかりやすい病気の一つで、高齢になるほど発症リスクが高まります。腎臓は一度機能が低下すると元に戻らないため、早期発見と進行を遅らせるためのケアが非常に重要です。
発症しやすい年齢: 7歳以上のシニア猫に多く見られます。
症状: 初期はほとんど症状がありませんが、進行すると、水を飲む量が増える、おしっこの量が増える、食欲不振、体重減少、嘔吐、口内炎などが見られます。
予防法: 定期的な健康診断(特に7歳を過ぎたら年1〜2回)で、血液検査や尿検査を受けることが重要です。また、腎臓に負担をかけにくいリンやナトリウムが調整された食事を与えることも有効です。日頃から猫が水を飲みやすい環境を整え、こまめな水分補給を促しましょう。
2. 下部尿路疾患(FLUTD)
膀胱や尿道に結石や炎症が起こる病気の総称です。特にオス猫は尿道が細いため、尿道閉塞を起こしやすく、命に関わる危険があります。
発症しやすい年齢: 2〜6歳の成猫に多く見られますが、子猫から高齢猫までどの年齢でも発症する可能性があります。
症状: トイレに頻繁に行くのに尿が出ていない、おしっこをする際に痛そうに鳴く、血尿が出る、トイレ以外の場所でおしっこをする、といった行動が見られます。
予防法: 水分摂取量を増やすことが最も効果的です。ウェットフードを取り入れたり、新鮮な水を複数箇所に置いたりしましょう。また、ストレスも原因となることがあるため、落ち着ける環境を整え、トイレを清潔に保つことが大切です。
3. 口内炎・歯周病
口の中に炎症が起こる病気です。歯垢や歯石が原因となることが多く、重度になると食事を摂ることすら困難になります。
発症しやすい年齢: 3歳以上の猫に多く、年齢が上がるほどリスクが高まります。
症状: 口臭がひどくなる、よだれが多い、食事を嫌がる、口元を触られるのを嫌がるなどのサインが見られます。
予防法: 毎日の歯磨きが最も効果的な予防法です。子猫の頃から歯磨きに慣れさせておきましょう。歯磨きが難しい場合は、歯磨き効果のあるおやつや、歯石がつきにくいドライフードを取り入れるのも良い方法です。定期的に動物病院で歯のチェックを受け、必要に応じて歯石除去を行いましょう。
我が家ではシートでの歯磨きですが、習慣化できましたよ!イケニャンは歯が命って言いながら、ゴシゴシしてます(笑)
4. 糖尿病
インスリンの作用不足や分泌不足により、血糖値が高くなる病気です。肥満が大きなリスク要因となります。
発症しやすい年齢: 8歳以上の猫に多く見られますが、若齢でも発症することがあります。
症状: 水を飲む量が増える(多飲)、おしっこの量が増える(多尿)、たくさん食べているのに体重が減る、ぐったりしている、といった症状が特徴的です。
予防法: 肥満を防ぐことが最大の予防法です。適切な食事管理と、適度な運動を心がけましょう。高タンパク質で低炭水化物のフードを選ぶことも有効です。定期的な健康診断で血糖値をチェックしてもらいましょう。
5. 甲状腺機能亢進症
甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気です。新陳代謝が異常に活発になり、様々な身体的変化を引き起こします。
発症しやすい年齢: 10歳以上の高齢猫に多く見られます。
症状: 食欲があるのに体重が減る、活動量が増えて落ち着きがなくなる、水をたくさん飲む、毛並みが悪くなる、嘔吐、下痢などが挙げられます。
予防法: 明確な予防法は確立されていませんが、早期発見が非常に重要です。高齢猫になったら、年に1〜2回の定期的な健康診断で、血液検査による甲状腺ホルモンの数値チェックを行いましょう。
まとめ
これらの病気は、早期に発見できれば進行を遅らせたり、症状をコントロールしたりすることが可能です。病気を隠しがちな猫様の異変に気づくためには、日頃から「多飲多尿」「食欲不振」「体重の変化」に注意し、定期的な健康診断を欠かさないことが何よりも大切です。猫様が健康で長生きできるよう、日々のケアと観察を丁寧に行いましょう。
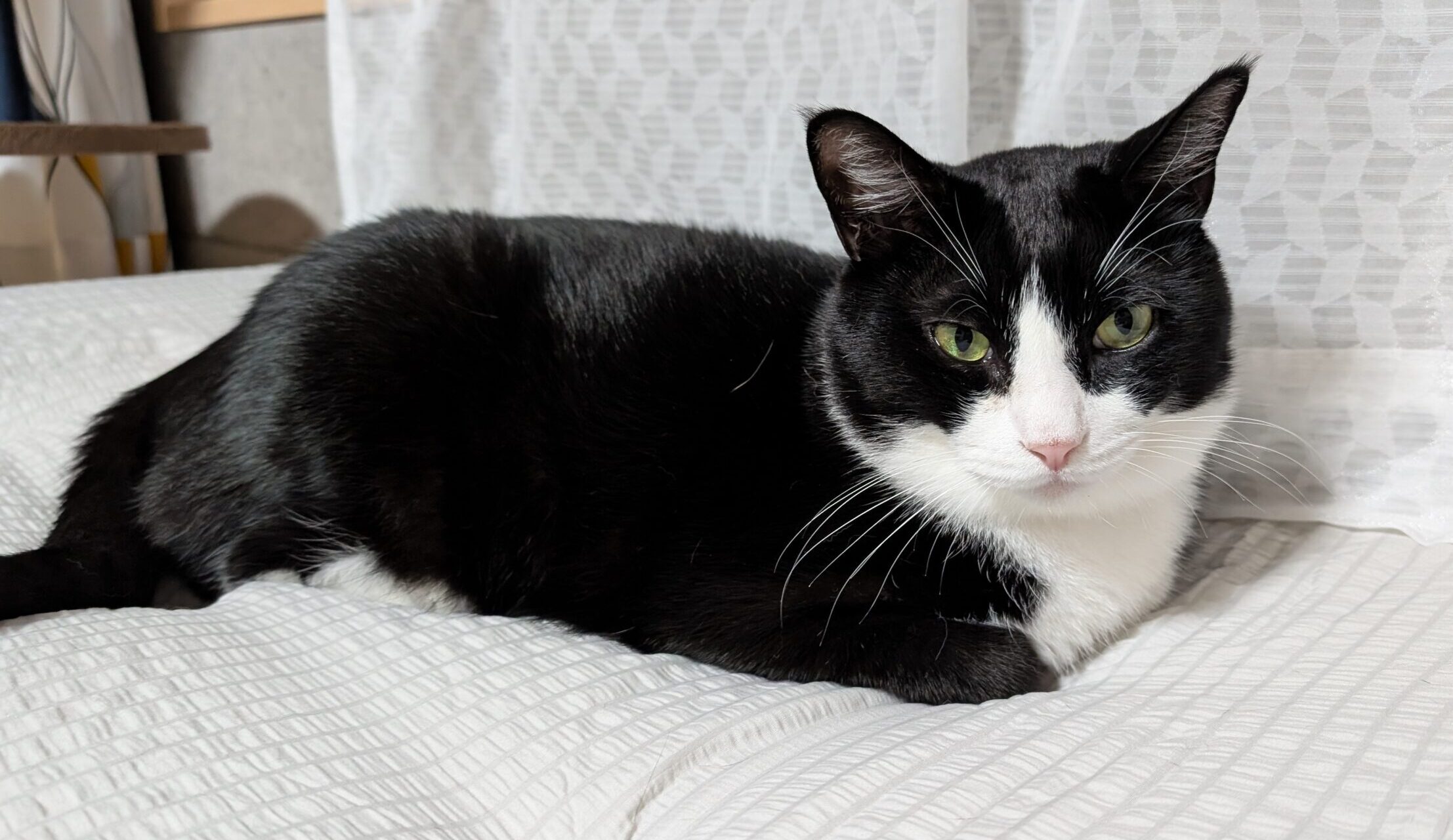


コメント