猫様のことを学ぼうと少し前に購入して放置していたねこ検定の本。
検定を受けるつもりはなく、猫のことを知りたいだけだったのですが、せっかくなので検定を受けてみようと思います。「ねこ検定」は、2017年3月26日に第1回目の試験が開催され、スタートしました。猫の生態や習性、健康管理に関する知識を問う検定で、猫との暮らしをより豊かにしたい人、これから猫を迎えたい人、そして猫に関する仕事を目指す人まで、幅広い猫好きに向けた検定として人気を集めています。
ここでは、ねこ検定について、試験内容、勉強法まで、合格に必要な情報をまとめます。猫様を知る第一歩として、猫おばさんと一緒に検定に挑戦しませんか。
1. グレードの種類とレベル
ねこ検定には、知識の深さに応じて3つのグレードが設けられています。
初級: 「ねこに興味がある人」向けの入門レベルです。猫の気持ち、食事、基本的な健康管理など、日々の暮らしに役立つ知識が中心です。猫を飼い始めたばかりの方や、これから飼う予定の方におすすめです。
中級: 「ねことの暮らしをさらに豊かにしたい人」向けのレベルです。猫の習性や体の仕組み、行動学など、一歩踏み込んだ内容を問われます。初級合格者や、猫との付き合いが長い飼い主さんの知識をさらに深めるのに適しています。
上級: 「ねこのスペシャリストを目指す人」向けの最上級レベルです。遺伝や繁殖、保護活動、倫理的な問題など、より専門的で幅広い知識が求められます。動物関連の仕事に就いている方や、深い知識を習得したい猫愛好家向けです。
最終的には、上級を目指したいと思ってます!
2. 公式テキストについて
ねこ検定の学習には、公式テキストが必須です。各級ごとに『ねこ検定公式ガイド&問題集』が販売されており、検定の出題範囲を網羅しています。私が持っているのは、初級ですね。これらのテキストは、猫の専門家によって監修されており、信頼性の高い情報が掲載されています。巻末には模擬試験もついているため、自分の実力を試すことができます。検定の合格を目指すなら、まずはこの公式テキストを手に入れることから始めましょう。ちなみに中上級はこちらです。
3. 検定の内容と出題範囲
検定は、すべての級で四肢択一のマークシート形式で行われます。オンライン試験の場合は、PC上で回答を選択する方式です。出題範囲は、公式テキストに沿って以下のようになります。
初級: 猫の生態(体の特徴、五感)、猫の気持ち(鳴き声、しぐさ)、食事、遊び方、お手入れ、病気のサインなど、基礎的な知識が問われます。
中級: 猫の歴史、品種、行動学、繁殖、多頭飼い、応急処置、健康チェックなど、より専門的な知識が加わります。
上級: 保護活動、猫に関する法律、遺伝性疾患、猫の行動修正など、高度な知識と倫理観が問われる内容です。
4. 試験日と試験の仕方
試験日: ねこ検定は、通常、年に1回、春頃に実施されることが多いです。詳しい日程は、主催者である「ねこ検定実行委員会」の公式サイトで発表されます。
会場受験: 東京、大阪、名古屋、福岡など、全国主要都市の会場で実施されます。筆記用具を持参してマークシートに記入する方式です。
オンライン受験: 自宅のPCから受験する方式も導入されています。自身の都合の良い場所で受験できる利点がありますが、事前に動作環境を確認しておく必要があります。
5. 勉強の仕方と必要な勉強時間
最も効果的な勉強法は、公式テキストを徹底的に読み込むことです。
全体を把握: まずはテキストをざっと読み、どのような内容が問われるのかを把握します。
深く読み込む: 次に、マーカーを引いたり、メモを取ったりしながら、内容を深く読み込みます。特に、数字や病名、行動学の専門用語などは、丁寧に覚えるようにしましょう。
問題集を活用: テキストの巻末にある問題集や、市販の予想問題を解いて、知識の定着度を確認します。間違えた問題は、なぜ間違えたのかをテキストに戻って確認し、理解を深めます。
初級・中級は独学でも十分合格を目指せますが、上級はより専門的な内容が多いため、必要に応じて関連書籍を読んだり、獣医師などの専門家の情報を参考にしたりすることも有効です。
合格に必要な勉強時間の目安
必要な勉強時間は、個人の知識レベルによって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
初級: 猫を飼っている方であれば、公式テキストを1〜2周するだけで合格できる方も多いです。目安は10〜20時間程度。
中級: テキストをしっかりと読み込み、内容を深く理解する必要があるため、初級より多くの時間が必要です。目安は30〜50時間程度。
上級: 専門的な知識が求められるため、公式テキストの範囲を超えた学習も必要になる場合があります。目安は50時間以上。
これらの時間はあくまで目安であり、猫との暮らしが長い方や、すでに専門的な知識をお持ちの方は、より短い時間で合格できる可能性もあります。しかし、どの級を受けるにしても、テキストをしっかりと読み込み、内容を理解することが合格への一番の近道となるでしょう。
まとめ
猫おばさんの挑戦、ねこ検定。自身で勉強したことをアウトプットすることで定着しますので、今後少しずつテキストを読み進めながら、学んだことをアウトプットしていこうと思っています!みなさん、一緒に勉強しましょう。猫様のよりよい生活のために♪

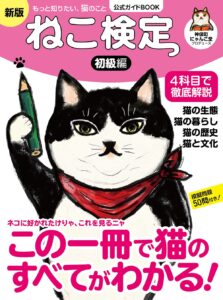
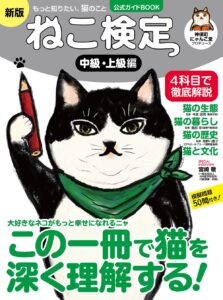


コメント